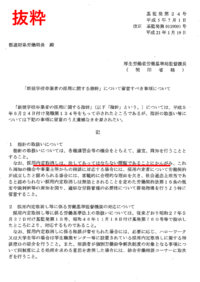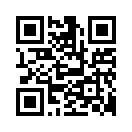2009年10月19日
鈴木勇次新会長ご挨拶

日本島嶼学会第4代会長に就任した鈴木勇次(長崎ウエスレヤン大学現代社会学部地域づくり学科教授)よりご挨拶を申し上げます。
写真の記事は,2009年10月04日久米仙社長から贈呈(写真撮影:山上博信)。
日本島嶼学会会長就任挨拶
鈴木 勇次(長崎ウエスレヤン大学)
2009年度久米島総会において会長に選出されました鈴木です。年齢はともかく研究実績においてあまりにも浅薄であることを考えますと、こうした役職は強く拒否すべきでありました。しかし、その術すら見出せないうちに持ち上げられてしまい、結果として承諾することになりました。きっと皆様にはご迷惑を山ほど掛けることになるかと思いますが、叱咤・叱正の程よろしくお願い申し上げます。
ところで、本学会は、島嶼学会とはいえ、見方によれば総合学会でもあります。会員の研究分野一つを取ってみても、国の内外を問わず極めて多岐に亘り、共通項は島嶼であるということのみです。大型島嶼、小型島嶼、孤立島嶼、群島島嶼など島嶼の存在位置により相違はありますが、相対的小地域である島嶼は、一定の制約条件の下で、人の生き方と自然環境が密接に関わって社会を形成しています。そこには一部の例外を除き、経済効率、開発優先より、むしろ自然との共生の中での智恵が継承されています。そして、これからの島嶼での生活は、都市生活とは違った生活重視の環境が求められると思います。そのためには何を実現することが必要であるかをそれぞれの専門分野から考えたいと思います。
しかし、グローバル化が急速に進展しはじめた今日、国境管理が問題視される一方で人々の自由交流・移動が盛んになり、国益保護と国際化が対峙し、政治的対応が改めて浮上しはじめています。「国境離島」など定義の難しい言葉も出始めています。そこでは、島嶼の役割が広義に解釈される可能性があります。すなわち生活との関連性の有無です。換言すれば無人島の役割が求められることになるかも知れないし、我々の研究対象外と目される人工島も遠からず俎上に上げられるかも知れません。
一方、身近な問題を見ますと、2013(平成25)年3月末で時限を迎える離島振興法の改正・延長問題、さらには、奄美、沖縄、小笠原振興法と離島振興法との関係など喫緊の課題もあります。我々は島嶼研究に携わる一人として、こうした課題等に対し何らかの形で発言する義務があるとも考えます。また、国際的には、日本国の離島振興方策が、島嶼振興の先進事例として関心を持たれています。底辺には、島嶼の「自立、依存」の課題があるようです。各国の島嶼研究者等との情報交換、交流がますます必要になってきます。
日本島嶼学会は、1998年7月創立以降本年で11年目を迎え、名実ともに研究団体としての真価が求められております。山階初代会長、竹内第2代会長、嘉数第3代会長の素晴らしい功績を汚さぬようにし、若手研究者の育成等内なる課題にも意を用いて頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
Posted by bonin at 16:51│Comments(0)
│日本島嶼学会
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。